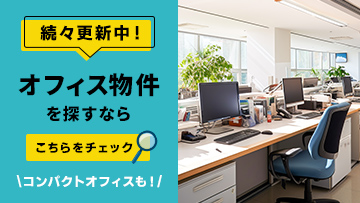会計上のルール「耐用年数」とは?
耐用年数とは、厨房設備や家電などの「資産価値」が保たれる期間のこと
耐用年数とは、飲食店で使用する厨房設備や家具、家電といった資産が会計上使えるとされる期間を指します。
国税庁では、事業で使う設備や機器、備品など、一部の資産は年月が経つにつれて価値が下がると定めています。このように、一定期間だけ本来の価値を維持する資産を「減価償却資産」と呼びます。
耐用年数は、この減価償却資産の「減価償却」が認められている期間です。国税庁のウェブサイトでは、設備ごとの耐用年数が公開されており、誰でも簡単に詳細を確認できます。
耐用年数と耐久年数の違い
| 耐用年数 | 法律で定められた、設備や機器が会計上その価値を維持できる期間 |
|---|---|
| 耐久年数 | メーカーが独自に設定した、設備や機器が問題なく使える期間の目安 |
耐用年数と似ている言葉に「耐久年数」があります。耐用年数は、法律で定められた資産を使用できる期間です。一方で耐久年数は、メーカーなどが「問題なく使用できる」と独自に定めた期間のことです。
耐久年数はあくまで使用の目安ですが、耐用年数は設備ごとに法律で年数が決まっているという点を覚えておきましょう。
国税庁が定める主要厨房機器の耐用年数

| 厨房機器 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 陳列棚、陳列ケース(冷凍機・冷蔵機付き) | 6年 |
| 冷房・暖房用機器 | 6年 |
| 電気冷蔵庫、電気洗濯機、その他類する電気・ガス機器 | 6年 |
| 氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式を除く) | 4年 |
| 食事・厨房用品(陶磁器製・ガラス製) | 2年 |
出典:国税庁「耐用年数(器具・備品)(その1)」
国税庁は、厨房設備の種類ごとに「法定耐用年数」を定めています。例えば、陳列棚や陳列ケース、電気冷蔵庫は6年、陶磁器やガラス製の厨房用品は2年とされています。
設備や製品によって耐用年数は異なりますので、ご自身の店舗の備品がどれに該当するか、確認しておきましょう。
厨房機器が耐用年数を超えていても大丈夫?故障や税金への影響
厨房機器の耐用年数が過ぎたからといって、耐久年数とは異なり、すぐに故障したり使えなくなったりするわけではありません。しかし、耐用年数が過ぎると、会計上その設備の資産価値は0になってしまいます。よって、耐用年数を過ぎたタイミングで厨房機器の買い替えを行えば、減価償却による節税を目指せるでしょう。減価償却の仕組みについては、次の章で詳しく解説します。
もちろん、耐用年数を過ぎると、徐々に故障のリスクが高くなるのも事実です。耐用年数を機に買い替えを検討し、営業中のトラブルを未然に防ぐことも重要な経営判断です。
厨房設備で賢く節税「減価償却」の仕組み

減価償却とは、厨房設備などの購入費用を、その資産の耐用年数に合わせて少しずつ経費として計上する会計上のルールです。
例えば、飲食店の業務用冷蔵庫を30万円で購入した場合、この費用を一括で経費に計上することはできません。法定耐用年数である「6年」にわたって分割し、毎年少しずつ経費として計上していく必要があります。
減価償却の対象となるのは、主に経年劣化を伴う高額な資産です。飲食店であれば、厨房機器や調理器具がこれに該当します。
なお、高額でも経年劣化しないものは減価償却の対象外です。決算の際には店の資産として計上するか、売却を行います。
| 対象となる資産 | 対象外となる資産 |
|---|---|
|
|
減価償却のメリット
減価償却は、会計上では厨房設備などの費用を支払ったものとして残りますが、実際に手元からお金が出ていくわけではありません。初年度に大きな出費がありますが、2年目以降は帳簿上のみの支出となるため、記載した分の金額を飲食店の資産として残すことができます。
耐用年数に応じて経費を計上することで、課税対象となる利益が減り、節税効果を得られるのが最大のメリットです。また、減価償却は、保有している資産の評価にも使用できます。
減価償却の計算方法
| 定額法 | 減価償却費=取得価額×定額法の償却率 |
|---|---|
| 定率法 | ①減価償却費=未償却残高×定率法の償却率 ②改定取得価額×改定償却率 ※①で償却保証額に届かなかった場合、②で算出 |
減価償却費は、「定額法」と「定率法」の2つの方法で計算できます。
定額法は、資産の取得にかかった費用を耐用年数で均等に分割し、毎年同じ金額を経費として計上する方法です。一方、定率法は、年度ごとに負担率を変えて経費計上する方法で、初年度の負担額が最も高く、年々低くなっていきます。
ソフトウェアや特許権などの無形固定資産や建物は定額法で算出するルールがありますが、その他は自由に選択可能です。ご自身の経営状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。
厨房設備を買い替える3つのタイミング

厨房設備は、耐用年数を目安にする以外に、設備の故障や事業の節目で買い替えるのがおすすめです。ここでは、厨房設備を買い替えるタイミングを3つご紹介します。
耐用年数を経過したとき
「耐用年数=故障する年数」ではありませんが、買い替えの目安として把握しておくと良いでしょう。
飲食店で使用する一般的な厨房設備の耐用年数は、6~8年のものが多いです。耐用年数を大幅に過ぎた古い設備は、売却価値がないケースも少なくありません。売却益が出ずに処分するとなると、別途費用が必要になってしまいます。
効率よく厨房設備を買い替えるためにも、耐用年数を一つの目安にしましょう。
厨房設備が故障したとき
厨房設備の故障も買い替えの良いタイミングです。製造から時間が経った設備の場合、修理を依頼しても交換部品がなく、修理を断られるケースがあります。大がかりな修理が必要な場合は、営業を一時的に止めなければならない可能性も出てきます。
飲食店の営業に支障をきたさないためにも、メーカーに故障時の対応がいつまでできるかなど、事前に確認しておくことが重要です。
また、「冷蔵庫が冷えにくい」「オーブンの電源が入りにくい」といった、厨房設備が故障する前の前兆がある場合は、早めの買い替えを検討しましょう。
事業の拡大・変更を計画しているとき
新規出店や事業内容を変更する際も、厨房設備を買い替える良い機会です。店舗のサイズや業務内容に合っていない厨房設備では、作業効率が悪くなり、オペレーションの悪化に繋がります。効率よく業務を行い、良いサービスを行うためにも買い替えがおすすめです。
また、居酒屋からカフェに業態を変えるなどの場合、既存の厨房設備をそのまま使い回すのは難しいでしょう。新しい事業に最適な厨房設備を導入するためには、店舗自体を移転することも一つの有効な選択肢となります。新しい場所で、新しい設備を導入することで、スムーズなスタートを切ることができます。
事業拡大・変更で店舗移転するなら「店舗買取り.com」
事業の拡大や変更は、新しい厨房設備を導入する絶好の機会です。新しい事業展開を見据えて店舗の移転を検討される経営者様も少なくありません。
しかし、新しい店舗への出店を考える際、今の店舗をどうするかお悩みではないでしょうか。退去にかかる費用や手続き、次の借り手探しなど、経営者様ご自身で対応するには大きな負担となります。
そんな時は、飲食店の退去・閉店に関するお悩みを解決する、当サイトの姉妹サイト「店舗買取り.com」にご相談ください。「居抜き売却」を活用して、造作や厨房機器をまとめて売却することで、撤退費用を抑えながら、次の出店資金を確保できます。

【おすすめポイント】
- 業界初「売却手数料0円」
- あなたに代わってテナント貸主と直接交渉
- 希望に合わせた売却先を見つけてくれる
「店舗買取り.com」では、業界初の売却手数料0円で、理想の売却を目指せます。居抜き売却を活用し、閉店時に発生する原状回復工事の費用負担を免除できる可能性があるだけでなく、専門知識が必要な「造作譲渡契約書」の作成や、テナント貸主との交渉も当社にお任せいただけます。
さらに、当サイト「居抜き店舗.com」に登録している80,000人以上の出店希望者の中から、次のテナント様を探すことで、より理想に近い金額での売却を実現します。
居抜き売却を相談する厨房設備の耐用年数を理解して、賢く節税しよう
厨房設備の耐用年数とは、その設備の価値が保たれる期間のことです。耐用年数は、厨房設備や備品の種類ごとに細かく定められています。
耐用年数が過ぎても、すぐにそれらの設備が使えなくなるわけではありません。しかし、耐用年数を一つの目安としてタイミングをみて、新しい厨房設備に買い替えることで、減価償却による節税効果が見込めます。
厨房設備以外に建物や内装が老朽化している場合は、新店舗への移転を考えるのも集客の面でも効果的です。飲食店舗の移転を行う際は、「居抜き売却」であれば、既存の店舗をただ閉店するのに比べて撤退費用を抑えやすく、設備や内装の売却益が入る可能性もあります。
コストをできる限り抑えて居抜き売却をしたい飲食店オーナー様は、ぜひ「店舗買取り.com」へご相談ください。
<お問い合わせ先>
フリーダイヤル|0120-3737-18
webでのお問い合わせはこちら


 友だち募集
友だち募集 お気に入り
お気に入り メッセージ
メッセージ
 保存した条件
保存した条件 マイページ
マイページ
 会員登録・ログイン
会員登録・ログイン ログイン
ログイン

















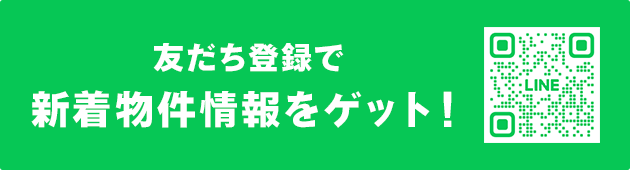









 居抜き物件を検索
居抜き物件を検索 駅・路線から探す
駅・路線から探す 地域から探す
地域から探す 業態から探す
業態から探す