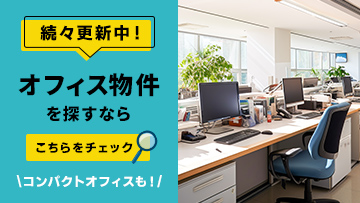「造作譲渡」とは?居抜き物件とスケルトン物件の決定的な違い
店舗や事務所の賃貸物件には、大きく「スケルトン物件」と「居抜き物件」の2種類があります。このうち、「居抜き物件」の取引を可能にするのが「造作譲渡」です。
| 物件の種類 | 特徴 | 造作譲渡の有無 |
|---|---|---|
| スケルトン物件 | 建物構造の躯体(くたい)のみが残された状態の物件。内装や設備は一切ない | 原則なし |
| 居抜き物件 | 前のテナントが使用していた内装や設備が残されている状態の物件 | 造作譲渡あり |
造作譲渡とは、物件自体の賃貸借契約とは別に、この残された内装や設備(造作)を、前の借主(譲渡側)と新たな借主(譲受側)との間で売買する手続きのことです。
居抜き物件を選ぶということは、この造作譲渡を行うことで、多額な内装工事費を削減し、すぐに事業を始められるというメリットを享受することに直結します。
【一覧】造作譲渡の対象になるもの・ならないもの
造作譲渡の対象は、店舗運営に欠かせない内装や設備ですが、所有権によって譲渡できるものが異なります。
| 対象区分 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 対象になるもの | 厨房機器、空調設備、カウンター、間仕切り壁、照明器具、顧客用テーブル・椅子など | 前の借主が費用をかけて設置し、所有権を持つもの |
| 対象にならないもの | 建物の柱や梁などの構造部分、床・壁の躯体(くたい)、貸主が設置した設備(既存のエレベーターなど) | 建物そのものに含まれるため、譲渡対象外 |
| 注意が必要なもの | リース契約の厨房機器、高額な医療機器、音響設備など | 所有権がリース会社にあるため、譲渡にはリース契約の処理が必須 |
造作譲渡のメリット・デメリット

実際に造作譲渡を活用するメリットと、考慮すべきデメリットを整理します。客観的に双方を把握し、判断材料として役立てましょう。
造作譲渡のメリット
造作譲渡の最大の魅力は、居抜き物件でスピーディーに開業・移転を実現し、初期コストを抑えられる点です。
1.入居側:初期投資を抑え、事業開始をスピードアップできる
厨房機器や内装のデザインなどを活かせるため、新規開業のための初期投資を大幅に削減できます。工事期間も短縮され、事業の立ち上げに要する期間も短くなります。
2.退去側:原状回復費用を大幅に削減できる
退去側が本来負担するはずだった内装の撤去(スケルトン戻し)費用を削減できます。設備や備品を買い取ってもらえることで、閉店時の資金的な負担も軽減できます。
3.時間的効率の向上
撤去作業や内装工事が一部省略できるため、退去側は閉店までの手間が大幅に減り、入居側は早期に店舗利用を開始できるため、双方にとって時間的効率が高まります。
4.内装や設備をそのまま再利用できる
利用可能な設備を再活用することで、廃棄物を減らし、持続可能な店舗運営にもつながります。
造作譲渡のデメリット
契約に関する多少の煩雑さからくるリスクも存在するため、事前の確認が必須です。
1.貸主の承諾が必要な場合がある
多くの場合、賃貸契約書において造作譲渡が禁止、あるいは事前承諾が必要と定められています。貸主が承諾しない場合、取引が成立せず、結局スケルトン状態に戻す必要が生じる可能性があります。
2.認識のずれによるトラブルリスク
譲渡対象の範囲や設備の状態について、売り手・買い手・貸主の間で明確に合意できていないと、後々トラブルに発展することがあります。例えば、「譲渡対象だと思ったらリース品だった」といった思い違いは少なくありません。
3.設備の老朽化リスクを負う
設備を引き継ぐことは、その設備の老朽化や故障リスクも引き継ぐことになります。譲渡額が安価でも、すぐに大規模な修繕費用が発生する可能性を考慮しなければなりません。
造作譲渡料の平均相場はいくらぐらい?
造作譲渡にかかる費用相場の目安と、どのように決定されるかなどを解説します。
造作譲渡料の相場は、立地や物件のサイズ、内装や設備の新しさ、業態など、さまざまな要素によって変動します。
一般的には数百万円単位(200万円〜300万円台)で取引されるケースが多いとされますが、駅前の好立地や、高価な調理機器・音響設備などが含まれる場合は、さらに高額になることも珍しくありません。
譲渡料を決定する主な要素
- ✓設備・内装の状態と耐用年数
新しい、またはメンテナンスが行き届いている設備は高額になります。 - ✓立地と集客力
好立地や、すぐに集客が見込める店舗は相場が高くなる傾向があります。 - ✓原状回復費用の削減効果
退去側が削減できる原状回復費用が大きいほど、譲渡料の交渉が成立しやすくなります。 - ✓売却・購入の緊急度
急いで手放したい、あるいは急いで開業したいなど、当事者双方の意向も大きく影響します。
実際には、専門の業者による査定や、双方の納得できる条件を見つけるための交渉が非常に重要になります。
【トラブルを防ぐ】造作譲渡を円滑に進めるポイント

スムーズに造作譲渡を成功させるために、押さえておくべき具体的なポイントをご紹介します。
1.【最重要】貸主とは時間に余裕を持ったコミュニケーションを
造作譲渡を急いで進めようとすると、契約内容や設備範囲の確認が不十分になりがちです。特に、造作譲渡は「貸主の承諾が降りて初めて成立する」という点を絶対に忘れてはいけません。
あらかじめ余裕のあるスケジュールを立て、貸主や仲介業者との信頼関係を築きながら、承諾を得る交渉を着実に進めることが成功の鍵となります。
2.「譲渡品リスト」と「設備の状態・履歴」を徹底チェック
事前に設備の契約形態を確認することで、思わぬ費用負担を回避できます。
リース品の有無
特に厨房機器や空調設備は高額リースである場合も多いため、所有権が誰にあるのかをしっかり調べましょう。リース契約の残債処理についても明確にしておく必要があります。
メンテナンス・故障履歴
設備のメンテナンス履歴や故障歴を把握することで、引き継いだ後の修理負担の予測もしやすくなります。実際に動作確認を行い、見た目だけでなく機能面での状態を把握することが重要です。
3.譲渡内容や処分方法の詳細を明確に書面化
造作のすべてを引き継ぐのか、一部だけを譲渡するのかといった点を漏れなく確認することが大切です。
例えば、古くなった設備を残すと後々トラブルの原因になるかもしれませんので、どの部分を処分し、どの部分を譲渡するのかをはっきり決めましょう。決定した内容は、「造作譲渡契約書」に明確に盛り込むことで、売り手と買い手の認識をしっかり揃えることができます。
4.信頼のおける業者へ依頼
造作譲渡は専門的な知識が必要とされるため、実績のある仲介業者やコンサルタントを通じて手続きを進める方法も有効です。
契約書の作成からリース品の確認、貸主との交渉まで一貫してサポートしてもらえるため、初心者でも安心して取引を行えます。依頼先を選ぶ際には、手数料やサポート内容、過去の実績などを総合的に検討することをおすすめします。
飲食店の造作譲渡をお考えなら「店舗買取り.com」へ!

飲食店の造作譲渡は、内装や厨房機器などの専門的な知識が必要となるケースが多く見られます。「店舗買取り.com」では、貸主との交渉や設備評価に精通したスタッフがサポートを行い、スピーディーな買取と譲渡を実現してくれます。飲食店ならではのリース契約や衛生面の問題なども相談に乗ってもらえるため、安心して進められる点が大きな魅力です。
造作譲渡についてよくあるQ&A
造作譲渡に関して、多く寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q.造作譲渡はトラブルになりやすい?
A.トラブルが起きる原因の多くは、設備や譲渡範囲における認識のずれです。例えば、引き渡されるはずだった機器がリース対象だったり、状態が説明と異なっていたりするケースがあります。事前に取引範囲と設備の状態を十分に確認し、契約書に明文化することでリスクを最小限に抑えることができます。
Q.造作譲渡契約書は誰が作るもの?
A.一般的には譲渡側と譲受側が協力して作成しますが、不安がある場合は専門家や仲介業者に依頼することが多いです。特に初めて行う場合、契約書の不備が後々のトラブルを生む原因になりかねないため、専門家のアドバイスを受けるのは有益です。
Q.造作譲渡はどのような流れで進める?
A.一般的な流れは以下の通りです。
- 1.貸主への事前相談・承諾を得る
- ↓
- 2.譲渡される設備や内装の範囲を確認
- ↓
- 3.譲渡料を決定し、交渉
- ↓
- 4.造作譲渡契約書の取り交わし
- ↓
- 5.設備の引き渡し、決済
すべての準備が整った段階で、新しい借主は設備を使って開業・移転に速やかに移行できます。
【まとめ】ポイントをおさえ、スムーズに造作譲渡を成功させよう
造作譲渡は、初期費用と時間を大幅に削減し、居抜き開業・移転の成功確率を高めるための強力な手段です。
最大のポイントは、「貸主の承諾」と「譲渡範囲の明確化」です。本記事で解説した注意点をしっかりと押さえ、時間に余裕を持って専門家(仲介業者)とも連携しながら進めることで、スムーズかつ安心できる取引を実現できます。
店舗買取り.comでは、飲食店舗の売却・撤退・閉店などを一貫してサポートします。業界初の「売却手数料0円」で、飲食店経営者様のお悩みに寄り添います。契約書の作成や交渉など、慣れない作業も行いますので安心してお任せください。コストをできる限り抑えて、早期に店舗を売却したいオーナー様は、まずはお気軽にご相談ください。
居抜き売却を相談する<お問い合わせ先>
フリーダイヤル|0120-3737-18
webでのお問い合わせはこちら


 友だち募集
友だち募集 お気に入り
お気に入り メッセージ
メッセージ
 保存した条件
保存した条件 マイページ
マイページ
 会員登録・ログイン
会員登録・ログイン ログイン
ログイン


















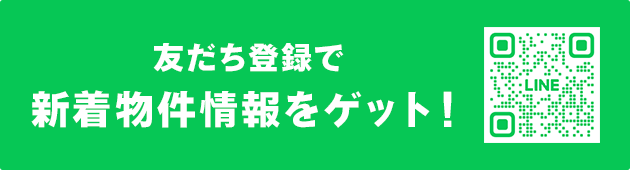









 居抜き物件を検索
居抜き物件を検索 駅・路線から探す
駅・路線から探す 地域から探す
地域から探す 業態から探す
業態から探す