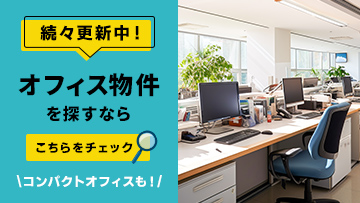飲食店経営を始めるための5ステップ

飲食店開業をスムーズに進めるには、以下の5つのステップを順序立てて実行することが重要です。
- STEP1:コンセプト・事業計画を立てる
- STEP2:飲食店の物件を探す(立地選定)
- STEP3:開店資金を準備する(資金調達)
- STEP4:開店準備(内装・設備・採用)
- STEP5:各種申請や届出を行う(法的準備)
STEP1:コンセプト・事業計画を立てる
開業準備で最も重要なのが、お店の「軸」となるコンセプトと事業計画の策定です。ここが曖昧だと、後の集客や経営戦略がブレてしまい成功が遠のいてしまうので、この時点でしっかりと軸を固めていきましょう。
コンセプトの明確化
「どのような顧客に」「どのようなメニューやサービスを」「どのような空間で提供するか」を具体的に定義します。特に以下の要素を5W1Hで細かく洗い出しましょう。
| ・ターゲット (Who):誰に? |
| ・提供物 (What):何を? |
| ・場所 (Where):どこで?(エリア) |
| ・時間 (When):いつ? (営業時間・シーン) |
| ・目的 (Why):なぜその店が必要か? |
| ・方法 (How):どうやって? (接客スタイル、内装) |
事業計画書の作成
コンセプトを基に、具体的な経営計画を事業計画書として文書化します。金融機関からの融資を受ける際にも必須の書類です。
| 【事業計画書に盛り込む主な要素】 |
| ・開業の動機、ビジョン |
| ・店舗の基本情報(場所、規模など) |
| ・提供するメニューやサービスの詳細 |
| ・収支計画(売上見込み、原価率、人件費など) |
| ・資金計画(必要資金と調達方法) |
| ・雇用計画、マーケティング戦略 |
STEP2:飲食店の物件を探す(立地選定)
物件選びは、飲食店の売上を大きく左右する最重要要素です。融資審査においても物件が決まっている方が有利になる場合があるため、コンセプトと並行して目星をつけておきましょう。
物件選びのポイント
- 商圏マーケティング:
駅からの距離、周辺のライバル店の状況、ターゲット顧客層の多さなどを徹底的に調査します。 - 業態との相性:
テイクアウト中心なら視認性の高い路面店、隠れ家なら少し奥まった立地など、コンセプトに合った条件を検討します。
ステップ3:開店資金を準備する(資金調達)
店舗の規模や地域によりますが、飲食店開業には一般的に1,000万円程度の資金が必要とされています。
資金調達の方法
開業資金を準備する方法としては、まず自己資金(貯蓄や家族からの支援など)を確保し、不足分を融資(日本政策金融公庫や銀行などからの借入れ)で補うのが一般的です。さらに、国や自治体の補助金・助成金制度も積極的に活用を検討すべき重要な資金調達源となりますので、利用条件を事前に確認しましょう。
「運転資金」の確保
開業直後からすぐに黒字経営になるとは限りません。初期投資(開店資金)とは別に、家賃、人件費、仕入れなどの数カ月分の運転資金も準備しておくことで、安定した経営の土台が作れます。
ステップ4:開店準備(内装・設備・採用)
資金と物件の目処が立ったら、いよいよオープンに向けた具体的な準備です。
| 【開店準備の主な内容】 |
| ✓内装・外装工事:コンセプトに基づいたデザインと施工。 |
| ✓厨房機器の設置:調理に必要な機器(コンロ、冷蔵庫など)の手配。中古品やリースも検討し、コストを抑える工夫も重要です。 |
| ✓備品・什器の購入:テーブル、椅子、食器、レジスターなど。 |
| ✓インフラ整備:電気、ガス、水道、インターネットの利用手続き。 |
| ✓従業員の採用:求人活動、面接、教育。 |
業務量が多くなるため、チェックリストを作成し、一つずつ漏れなく進行させることが成功の鍵です。
ステップ5:各種申請や届出を行う(法的準備)
お店の準備と並行して、法律に基づいた公的機関への各種届出・申請が必要です。これを忘れると営業が開始できませんので、余裕を持って準備しましょう。
必須の主な申請・届出一覧
| 必要な書類 | 提出先 | 目的・備考 |
|---|---|---|
| 営業許可申請書・営業届 | 保健所 | 飲食店営業の許可と食品衛生責任者の設置に必須。 |
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 税務署 | 開業後1ヵ月以内に提出。青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」も。 |
| 防火管理者選任届出書 | 消防署 | 特定の規模以上の店舗に必須。防火管理者の資格が必要。 |
| 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 | 警察署 | 深夜0時以降にお酒を提供する居酒屋などが対象。 |
申請手続きは、提出先ごとに異なるため、事前に確認し、余裕をもって対応することが重要です。 これらのステップを確実に踏むことで、飲食店開業はスムーズに進み、成功への道筋が見えてきます。
飲食店経営に必須の資格
調理師免許は必須ではありませんが、以下の2つの資格は、飲食店を経営・営業するために必ず必要となります
1. 食品衛生責任者
食品を扱う店舗の衛生管理を行う責任者です。
・取得方法: 各都道府県知事が実施する約6時間程度の講習会を受講する。
・免除対象: 栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格保有者は講習が免除されます。
| 【講習会の受講が免除される人】 |
| ・栄養士 |
| ・調理師 |
| ・製菓衛生師 |
| ・船舶料理士 |
| ・と畜場法に規定する衛生管理責任者 |
| ・と畜場法に規定する作業衛生責任者 |
| ・食鳥処理衛生管理者 |
| ・食品衛生管理者または食品衛生監視員の資格要件を満たす者 |
2. 防火管理者
火災による被害を防止する役割を担い、適切な防火管理業務を実施します。
取得方法: 各都道府県知事等が実施する半日~2日間程度の講習会を受講する。
免除対象:すでに「消防設備点検資格者」や「自衛消防業務講習修了者」の資格を持っている場合は講習の一部科目が免除。
| 防火管理講習の種類 | 詳細 |
|---|---|
| 甲種防火管理新規講習 | 「甲種防火管理者」になるために必要。対象となる建物の延べ面積や収容人員に制限がない。(大規模な建物に対応) |
| 乙種防火管理講習 | 「乙種防火管理者」になるために必要。管理できる防火対象物の面積や収容人員に制限がある。 |
| 甲種防火管理再講習 | 「甲種防火管理者」の資格の更新・知識の再確認のための行う。義務対象施設の場合は一定期間ごとの受講が義務付けられている。 |
飲食店開業に必要な費用と初期投資を抑える方法

飲食店を開業する際に必要な初期費用は、一般的に1,000万円前後が目安とされています。ただし、この金額はあくまで目安であり、店舗の規模やコンセプト、特に都心部での開業では、さらに高額になる傾向があります。
必要な初期投資は、大きく分けて以下の3つの要素で構成されます。
1.物件の初期費用:
家賃、敷金、保証金(物件取得費)など。地域や契約内容によって大きく変動します。
2.店舗の設備導入費用(設備資金):
内装・外装工事費、厨房機器(コンロ、冷蔵庫など)の設置費用。
3.什器・備品の購入費用:
テーブル、椅子、食器、調理器具、レジシステムなどの購入費用。
初期費用を効果的に抑える工夫
開業時の経済的な負担を軽減し、運転資金に余裕を持たせるためにも、初期投資のコストダウンは重要です。
| 「居抜き物件」を選ぶ | 前の店舗の内装や設備をそのまま引き継げるため、大幅に初期投資を削減できます。 |
| リース品・中古品を活用する | 厨房機器や家具などを新品で揃えるのではなく、中古品やリースを利用することで、一度にかかる費用を抑えられます。 |
賢く費用を管理し、初期投資を最適化することで、より安定した飲食店経営をスタートさせることが可能になります。
飲食店経営が厳しくなる主な要因と業界の現状
経営が厳しくなる主な理由
| 要因 | 詳細 |
|---|---|
| 競争の激化 | 開業が多いためライバル店が多く、顧客の奪い合いが発生しやすい。 |
| コンセプトの曖昧さ | ターゲット層が定まらず、効果的な集客やPRができない。 |
| 収支管理の不徹底 | 人件費や原材料費などのコスト管理が甘く、利益構造を把握できていない。 |
| サービスの質・店舗環境 | サービスや商品の質が価格に見合わない、または店内が不衛生など、顧客満足度が低い。 |
| 外的要因 | コロナ禍のような社会情勢や経済環境の急激な変化。 |
日本の飲食店経営は、2025年に入っても依然として非常に厳しい状況にあり、「宿泊業、飲食サービス業」の倒産件数は、2023年、2024年と過去最多のペースで推移しており(※帝国データバンクなどの調査)、この厳しい流れは2025年も変わらないと見られています。
倒産件数の報道を目にすると不安になるかもしれませんが、裏を返せば「どこにでもあるお店」は淘汰され、「個性が際立つお店」が強く求められる時代になったということです。 単においしいだけでなく、コンセプトをしっかり構築し、お客様が「誰かに話したくなる」「写真を撮りたくなる」ようなお店の世界観・接客サービスで、唯一無二の特別な「顧客体験」を生み出したり、時代のニーズを取り入れていくことで、他店との差別化をしていく必要があります。
それだけではなく、収支管理の不徹底、デジタル化への遅れなど、根本的な原因が潜んでいるケースも大いに考えられます。それらを一つ一つ解決していく地道な努力が、お店の永続的な経営へと繋がります。また、メニューやオペレーションの簡素化、IT活用による業務効率化といった改善策も練り、実行することで、経営の立て直しは十分に可能です。
一見厳しい課題も、お店をより強く、より魅力的にするためのヒント・チャンスと捉えていく事が成功への近道です。
※出典:中小企業庁「2022年版 小規模企業白書」より
経営が厳しいときの立て直し策
自社に原因がある場合は、原因を特定し、以下の5つのような具体的な改善策を講じることで立て直しが可能です。
1. コンセプトの練り直し
曖昧なコンセプトでは集客はできません。現在の状況を分析し、5W1Hでターゲットや提供価値を再定義しましょう。トレンドや自店の強みを活かせるかどうかも重要です。
2. メニュー・サービス内容の見直し
価格に見合った質の担保ができているか、古くなったメニューを更新しているかを確認します。また、基本的なことですが、店内の清潔さや従業員の接客態度が顧客満足度に大きく影響することを忘れずにいましょう。
3. 収支の適切な把握と管理
売上、客単価、原価コスト(FLコスト)、固定費、変動費、損益分岐点などを正確に把握しましょう。売上を伸ばす努力と同時に、無駄な支出を削減することも経営改善には不可欠です。
4.デジタルツールの導入
モバイルオーダー、配膳ロボット、在庫・発注管理システムなどを積極的に取り入れることで、人件費やタイムロスを削減でき、少人数でも質の高いサービスを提供することができます。
5.移転や閉店も視野に入れる
あらゆる改善策を講じても経営の立て直しが難しいと判断した場合、賃料の安い物件への移転や閉店を決断することも賢明な選択です。資金が尽きる前に撤退することで、赤字の拡大を抑え、次のステップへの余裕を持てます。
賢い移転・撤退方法:「居抜き売却」のススメ
それでも経営がうまく立ち行かなくなり、移転や閉店を決断した際は、「居抜き売却」を考える事も一つの方法です。
撤退の際、通常は原状回復工事(借りた時の状態に戻す工事)が必要となり、多額の費用が発生します。この費用を大幅に抑えることができるのが、居抜き売却です。
居抜き売却のメリット
厨房設備や内装をそのまま残して次の借主に売却するため、原状回復工事費用を最低限、または不要にできます。結果として、費用を抑えて早期に移転・閉店・撤退が可能になります。
「居抜き売却」にはさまざまな手続きが必要なため、専門業者に依頼するのがおすすめ。経験や実績が豊富な「店舗買取り.com」は、業界初の売却手数料0円に加え、オーナー様にとって様々なメリットがあり、スムーズな売却が可能です。
「店舗買取り.com」を活用するメリット

「店舗買取り.com」は、飲食店の撤退・売却をサポートするサービスです。
- 売却手数料0円
- 貸主との直接交渉をサポート
- 理想の売却先を探してくれる
豊富な実績があり、売却手数料0円で利用できるのが大きな強みです。
居抜き売却をする事で、移転・閉店時の高額な原状回復工事が不要になり、経営の負担を減らせます。また、貸主との交渉や「造作譲渡契約書」の作成など、専門的な手続きも代行してくれるため、安心して任せることができます。10万人以上の出店希望者が登録する「居抜き店舗.com」と連携し、最適な売却先を見つけてくれる点も魅力です。
居抜き売却を相談する飲食店経営に関するQ&A
Q. 飲食店経営者は儲かりますか?
A. 経営が順調に進めば儲かる可能性はあります。
ただし、店舗規模や業態によって利益率は大きく異なるため、「必ず儲かる」とは限りません。成功するには、常に経営を学び、売上向上とコスト管理の工夫を継続する必要があります。
Q. 飲食店経営に向いている人の特徴は?
A. 計画性、責任感があり、変化に柔軟に対応できる人です。
売上に波があるのが一般的なため、一喜一憂せず、常に先を見据えた計画的な行動が求められます。
Q. 飲食店経営のコツは?
A. 明確なコンセプト設計と、それに基づいた一貫性のあるサービス提供です。
コンセプトを詳細に設計し、メニューや内装、集客、従業員のマネジメントまですべてをテーマに沿って行うことで、成功の確率は高まります。
Q. 飲食店経営が厳しくなったときは、どうすればいいですか?
A. まずは経営悪化の原因を徹底的に究明し、以下の3つの立て直し策を講じましょう。
1.根本的な原因の特定とコンセプトの再設計
2.収支管理の徹底的な見直し(金銭面のチェック)
3.移転・撤退(閉店)の判断を視野に入れる
まとめ:移転・売却・撤退も賢い判断
飲食店経営は簡単ではなく、開業前の準備や資格取得はもちろん、開業後の厳しい競争を勝ち抜くための経営努力が常に求められます。もし経営が厳しくなった場合は、早めに立て直し策を講じましょう。それでも再起が難しいと判断した際は、赤字を増やさないための「移転・売却・撤退」も、リスクを最小限に抑える賢い判断の一つです。
コストを抑えて円満な移転や撤退を目指すなら、居抜き売却を検討し、「店舗買取り.com」のような専門サービスに相談することをおすすめします。
<お問い合わせ先>
フリーダイヤル|0120-3737-18
webでのお問い合わせはこちら


 友だち募集
友だち募集 お気に入り
お気に入り メッセージ
メッセージ
 保存した条件
保存した条件 マイページ
マイページ
 会員登録・ログイン
会員登録・ログイン ログイン
ログイン














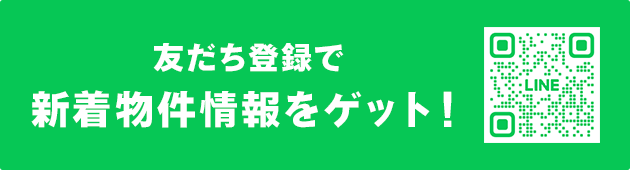









 居抜き物件を検索
居抜き物件を検索 駅・路線から探す
駅・路線から探す 地域から探す
地域から探す 業態から探す
業態から探す